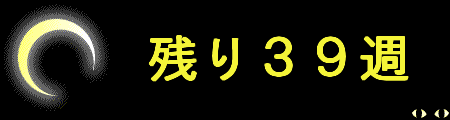☆ 11月第3週 ☆ 2014/11/13 ~ 11/19
安楽死を考える : 『尊厳死』との違い
安楽死と関連して、『尊厳死』という言葉があります。 2つの言葉は、似ているようで全く違ったものだと言えます。 安楽死が、積極的な『死に至る薬物投与』つまり『(死の)引き金』であるのに対して、 尊厳死とは、『延命処置の辞退』という『(消極的な)治療方針への希望表明』であり、 医師・医療機関に対して『苦痛の除去のみを要請』するものだとされています。 『尊厳死』に関しては、本人(および家族など)の正常な判断機能が明らかな限り、 医師・医療機関がその要請に応えた範囲での施療をすることに、犯罪性・責任追及は ないものだとされています。 それだけに、早い時期から作成することができるものであり、 いわば、その人の「死生観」の表明でもあるのです。 日本でも 「尊厳死協会」 という組織があり、医師・医療機関への意思表明の仕方などに 関して適切なアドバイスを行っています。 一方、「安楽死」に関しては、世界でもそれを認めている国・地域はまだ少数派で、 日本では本格的な議論も行われていないのが実情のようです。 宗教的な背景とか、いろいろな条件がクリアされるまでには、相当の時間を要する重い テーマだというのが、現状だと理解しています。 私は、このブログの最初の個所に、 『ターミナルケアに関する要望書』 を作成していることを 紹介しており、回復が望めない状況になった際には、そこに記したように「延命処置は不要、 痛みの緩和施療のみを希望」する旨、文書化しています。 これについては、女房と長男の署名も得て、いつでも医師・医療機関に提出できるように している訳です。 こうした『尊厳死に関する要望』は、日本でも少しづつ拡がり始めているようで、特段の 問題はない状況にあると思われます。 私の作成した『要望書』は、カトリックの司祭(松本信愛神父)が原案を示してくれたもので、 カトリック医師会大阪支部とも調整が行われていると承知しています。 なお、作成してから、かなりの年数が経過していますので、新しい日付で、再作成しておく ことが望ましいと思っています。 |
|
安楽死と尊厳死を混同している文章に時々出会います。 手元に配信されている「世界キリスト教 情報 第1242信(2014.11.10)」 でも、「バチカン 『生命アカデミー』会長が ”尊厳死” 批判」 と いう表現が用いられていますが、先週にも見たように、批判されているケースは「安楽死」であって 「尊厳死」 ではありません。 このようにこのテーマは、まだまだ多くの人々に正しく認識される ところまで至っていない事柄です。 正しい理解が広まることを期待しているところです。 |

プログラムで振り返るオペラ ② : ベルク 「ヴォツェック」
ベルクは、いわゆる現代音楽の作曲家です。 そのオペラ作品が演奏されることはそんなに多くはありません。 私は、たまたま若い時期に現代音楽に関心を寄せていましたので、この作品が日本初演された際に、 鑑賞する機会が持てたのでした。 その後、もう一度だけ大阪音楽大学のホールでの公演で、このオペラを見ています。
1963年の当日の、私の日記がブログで公開してあります。 当時の感想は そちら に譲ります。 今の目で読むと、何とも青臭い感想ですが、受けた衝撃の大きさは読み取っていただけるかと 思います。 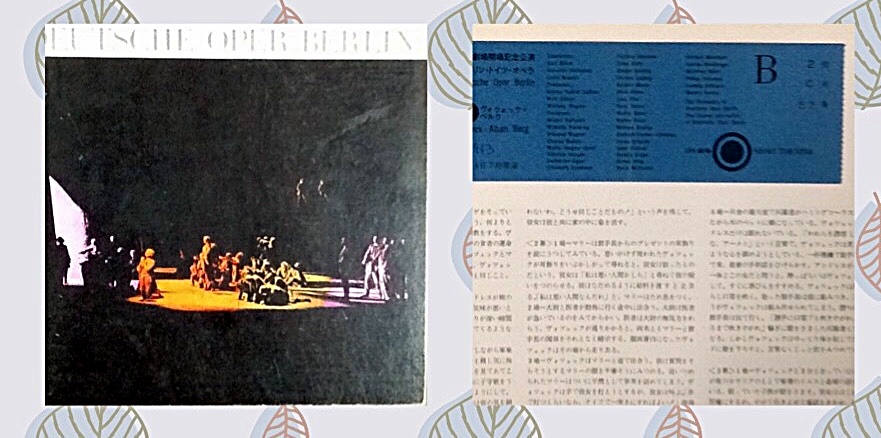 同じベルリン・ドイツ・オペラが演奏したLPの全曲盤を持っていました。 こちらは、タイトル・ロールを何と D.F=ディースカウが歌っているという豪華版。 指揮は、カール・ベーム。 LPでの大変な名盤でした。 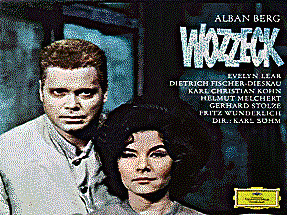 また、2004年の大阪での上演も、なかなかのものでした。 指揮は山下一史、タイトル・ロールは井原秀人、ほかに小餅谷哲男、西垣俊朗、田中友輝子など 関西の実力者を揃えた好演でした。 機会があれば、もう一度見たい「オペラ」 No.1 です。 |
| 今週の | 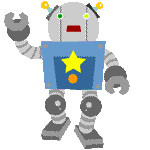 | 興味津々 | 通訳案内士(通訳ガイド) という国家試験があることを、最近知りました。 外国人観光客相手のプロの観光ガイドのことだそうです。 私の退職時(1990年)には思いもよらなかった国家資格です。 語学力・接客能力・歴史や地理の知識など、幅広い能力が求められます。 いろいろな旅行者とのふれあい、体力だけでなく、いろいろなトラブルへの 対応力など、求められる要件の多さが想像されます。 しかし、退職後に、もしもそういう間口の広い業務に携わったとしたら 全然別の第二の人生があったのだなぁと・・・ふと、羨ましく思えたのでした。 |