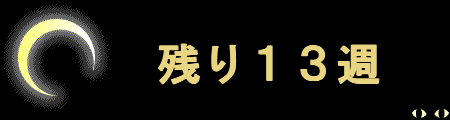☆ 9月第1週 ☆ 2015/08/27 ~ 09/02
不思議な福音書 ⑤ : 針の孔にらくだ のなぞ
今回は、マタイ19章24節の 「金持ちと神の国」 の話題です。
重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。 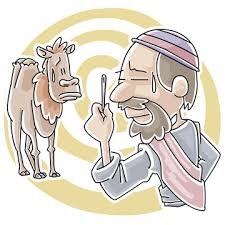 この個所に関しては、「翻訳」における疑問はありません。 ギリシア語聖書には、まちがいなく 「らくだ」 が 登場しているのです。 ところが、この有名なフレーズに なぜ 「らくだ」 が登場するのか という疑問を抱かせ、それに答えて下さる 先生がいるのです。 このブログの 「2014年 10月第1週」 ですでに紹介済みのものです。 これまで、『ギリシア語で書かれた聖書』 ばかりを取り上げてきましたが、実は、世界には「ギリシア語聖書」 に依存しない、独自の福音書(など)が存在するのだそうです。 当時の地中海世界では、ギリシア語は国際語として広く使われていたようです。 余談ですが、E U に ギリシアが加入しているのも、「西洋文明の偉大な先達」 への配慮からだと言われています。 新約聖書の中(マタイ 21:12)に、「神殿に捧げる貨幣の両替屋」 のことが記されています。 それから、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、 両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。 当時のユダヤでは、ドラクマというギリシアの通貨が日常的に使われていたそうですが、神殿内では 古代テュロスの貨幣の使用のみが認められていたので、そのための両替が必要だったという訳です。 ここから、当時のユダヤには、ギリシアの文化(言語も含めて)が広まっていたことが分かります。 ルカ福音書 15章8節には、ドラクマ硬貨をなくした女の 「たとえ話」 が出てきます。 また、使徒たちの宣教 6:1 にも、生まれたばかりのエルサレムの教会に関して、 そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に 対して苦情が出た。 それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじられていたから である。 という記述があるように、当時のエルサレムのユダヤ人社会では、ヘブライ語を使う人のほかに、ギリ シア語を日常的に使用していた人々がいたことが伺えます。 先ほどの、2014/10 第1週のブログで紹介した 竹田先生によると、ヘブライ語という言い方は不正確で、 むしろ
ということだそうです。 問題は、言葉としての 「アラム語」 と 「シリア語」 との関係で、実はほとんど同じ言語だとのこと。 先に見たように「使徒たちの宣教」では、「ヘブライ語を話すユダヤ人」 という表現がありますが、 正しくは「アラム語を話すユダヤ人」 で、それは「シリア語」とほぼ同じもの。 彼らはそれをヘブライ 文字で記録していたということのようです。 西暦 70年のエルサレム陥落で、エルサレムを中心としたキリスト教徒は、姿を消してしまいます。 一方、ギリシア語を話すキリスト教徒は、地中海世界で次第に広がりを見せるというように対照的な 運命をたどることになるのでした。 そういう訳で 『ヘブライ語を話すユダヤ人』 キリスト教徒の姿は、現時点では全くとらえることができ ないのです。 ところが、ユダヤ人が話していたアラム語とほぼ同じシリア語を話すキリスト教徒たちは、 シリアだけでなく周辺の地域に、今も存在し続けているとのこと。 彼らの使う文字は「フェニキア文字」ですが、それで記述された 「聖書」 が現在でも受け継がれている のだそうです。 その「聖書」で、今取り上げている個所を見ると、彼らはそれを決して 「らくだ」 とは 受け止めてはおらず、 素直に『ロープ』 と理解しているというのです。 というのも、シリア語では、「ロープ」 と 「らくだ」 とは同じ発音であり、この個所を 「らくだ」 と 理解する人は皆無で、「ロープ」 と受けとめるのがきわめて当然 ・・・ ということなのです。 日本語でも、「あめ」という発音からは「雨」「飴」という2つの単語が思い起こせますが、 「そらがくもって、やがてあめがふってきた」 というフレーズで、「飴」 という文字を イメージする人はいないでしょう。 『雨』 と思うのが常識です。 同様のことは、「橋」「箸」「端」 などでも言えることで、文脈を見れば、それがどの 「はし」 を表現しているかは、自明のことがら というべきでしょう。 そういえば、一休さんのとんち話に、「このはし、わたるべからず」というのがありました。 (^_^); イエスはユダヤ人ですから、日常的にはアラム語 (これは言葉としてのシリア語とほとんど同じ! ) を 用いて話していたと考えられます。 問題のフレーズでの単語が、「らくだ」 なのか、「ロープ」なのか は、聴衆の耳には素直に区別されていたことでしょう。 だからこそ、シリア語の聖書を読む人々は 現代でも、それを 「ロープ」 と受けとるのが 『常識』 だという訳です。 ところが、ギリシア語を母語とするキリスト教徒の誰かさんが、アラム語のこの単語に、2つの意味が あるということに気づかず、単純に 「らくだ」 という文字を当てはめてギリシア語化(文書化) した とすれば、イエスのことばとは全く別の、「針の穴にらくだ」 という言葉遣いで、広くギリジア語世界に拡散 したとしても不思議はないことになります。 そういうギリシア語聖書をもとに、世界の各言語に 「らくだ」 のエピソードはますます広がり、私たちも 日本語聖書でそれを読み、「針の穴にらくだ」 というたとえ話として定着してしまったということです。 私の言いたいことは、こうです。 聖書の底本を確定するという学者の熱意はそれはそれでよろしいでしょう。 ただ、ギリシア語聖書をいかに厳密に研究しても、それはしょせんギリシア語の世界。 イエスご自身は、アラム語(シリア語とほぼ同じ発音)で人々に話されていた。 イエスの言葉づかいを、ギリシア語聖書が正しく伝えているとはいえないことが 今回のケースから判明した以上、ギリシア語聖書の研究だけでは、本当のイエスの姿や 『ことば』 には到達できない「ケース」 ないし 「可能性」 がある。 つまり、ギリシア語ベースの聖書研究はそれはそれで結構だけれど、それでイエスの実像に迫ること が十全かといえば決してそうではない。 ギリシア語聖書をどう正しく読み込んだとしても、このケース ではイエスの本当の言葉(遣い)にたどり着くことはできない ・・・ という大事なポイントが、この事例 から見えて来るというわけです。 何が正統信仰かなどという議論は、しかるべき人々にお任せして、私は、そういう議論を参考にしつつも 自分の感性で、『イエス』 というお方のメッセージと生き方 ・ 死にざまを、自分なりに追い求め、いくらか でも、それに倣うことができれば ・・・ と願いつつ、日々の歩み・信仰生活を続けているのです。 大事なことは、『キリスト教』 ではなく、『イエス 本人』 との出会いとそれに基づく信仰生活。 教会・キリスト教は、イエスに出会うための 『学校』 です。 そして学校はいずれ卒業していくもの! ここに私の信仰、イエス理解のベースがあります。 暑いさなか、ながながと、このテーマにおつきあいいただき有難うございました。 |

| 今週の | 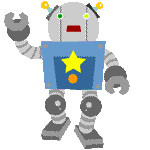 | いい話 | 高校野球 決勝戦で敗れた仙台育英。 キャプテンの佐々木君は、これを機に野球をやめ、就職の途を選ぶ とのこと。 母親に苦労をかけ続けだったので、親孝行をするというその決意。  私の子供のころならどこにでもあった話ですが、今どきの若者がこういう決断を したとは何とも感動的。 希望する「消防士」への道をしっかりと歩んでほしいと、こころから応援しています。 |