☆ 7月第4週 ☆ 2014/7/17 〜 7/23
「秋の空」と聞いて、すぐに連想するのが「女心(あるいは男心)」。 しかし、この詞にはとてもそういう雰囲気はありません。 また、「秋」といえば、「天高く馬肥ゆる」とか、「豊かな実りの季節」「澄みきった空」といった イメージが浮かびますが、そんな様子も全く見当たりません。 一体「耐えがたいほどの(秋の)激しさ」とは何なのか? これが第一の疑問点です。 いわゆる日本人の季節感とは全く違う事柄を指しているのではないか? そういえば、八木重吉は、クリスチャンでした。 そこから連想したのが「人生の秋へ」という ホイヴェルス神父の著書です。 八木重吉とホイヴェルス神父とに接点があったのかどうかは別にして、ヨーロッパの宗教的感性と いった点に、詞を読み解くヒントがあるのかも・・・と想像してみました。 ホイヴェルス神父の上記著書の中に、次のような個所があるようです。 旧約聖書:コヘレトの言葉12章からの引用の後、ドイツの友人から貰った詩を紹介しています。 最上のわざ この世の最上のわざは何? 楽しい心で年をとり 働きたいけれども休み しゃべりたいけれども黙り 失望しそうな時に希望し 従順に、平静におのれの十字架をになう 若者が元気いっぱいで神の道をあゆむのを見つけても妬まず 人のために働くよりも、謙虚に人の世話になり、 弱って、もはや人のために役たたずとも 親切で柔和であること。 老いの重荷は神の賜物 古びた心に、これで最後の磨きをかける まことの故郷へ行くために おのれをこの世につなぐくさりを少しづつ はずしていくのは、真にえらい仕事。 こうして何もできなくなれば それを謙遜に承諾するのだ。 神は最後に一番よい仕事を残してくださる。 それは祈りだ。 手は何もできない。けれども最後まで合掌できる。 愛するすべての人の上に、神の恵みを求めるために。 すべてをなし終えたら、臨終の床に神の声をきくだろう。 「子よ、わが友よ、われ汝を見捨てじ」と。 次に、第二の疑問点は、空との対話の中で使われている「そのみどりのなかへ」の<みどり> という単語です。 空が緑色であろうはずはなく、むしろ「青」ではないのか? どうも「みどり」には、「緑」の文字ではなく、「翠」とか「碧」の文字をイメージする方が適当なの かも? など・・・ 以上を踏まえて、私なりに、こう考えてみました。 「秋」は、人生の秋=老い or 死への誘い。 死後は「冬」、朽ちた肉体は墓石の下。 秋になると、荒々しい激しさで、死への誘いの声が聞こえてくる。 こころは、怖れ慄き 逃げ場を求める。 あの碧色(みどり)の空に浮かぶ雲の上に、こころ安らぐところがあるのではないか・・・ 息を引き取るその時までのいっときの間、雲の上に私のこころを匿って欲しい。 死後は、冬の凍てついた土の下に眠っても構わないから・・・ 結局のところ、カウントダウン中の私は、この詞を、こういう文脈の中で解釈することにしました。 八木重吉のイメージと違うかもしれません。 作曲者の意図から離れているかもしれません。 しかし、79歳の私には、こうイメージすることが、一番しっくりと来るように思えたのでした。 |
レクィエム : 指揮者 ロリーン・マゼール
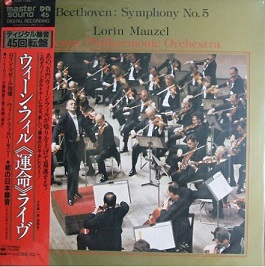 |
指揮者 マゼールさんが 7/13 に亡くなったとのこと。 最初に彼の指揮を聴いたのは、1963.11 東京交響楽団の定期演奏会 でした。 若い溌剌とした姿が目に焼き付いています。 その後も、バイエルン放送交響楽団と2度・フィルハーモニア管弦楽団 と2度・ピッツバーグ交響楽団を率いての来日公演を聴く機会があり ました。 ピッツバーグ響とは、阪神淡路大震災の被災地・神戸でのチャリティ・ コンサートでした。 LP・CD も、オペラ「カルメン」を2組(J.M.ジョンソン&P.ドミンゴ、フランス 国立管と、A.モッフォ&F.コレルリ、ベルリン・ドイツ・オペラ管)、マーラー 9番&10番、ベートーヴェン5番など・・・多数。 「運命」のウィーン・フィルとのものは、45回転LP(12インチ)という珍品。 (高音質の追求) ご冥福をお祈りします。 私の LP / CD コレクションを無償でお譲りします。
|
| 今週の | 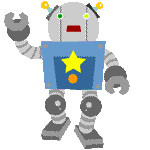 | いちおし 写 真 |
今年も、庭で蝉の抜け 殻を9個発見。 あのうるさいほどの大 合唱に加わっているん ですね。(^_^); |
   |

