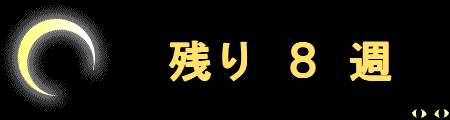☆ 10月第1週 ☆ 2015/10/01 〜 10/07
思い込み : キリスト教とはどんなもの?
先週のページの最後に取り上げた、「今週の面白〜い」。 いかがだったでしょうか?
ああいう設問があると、人はついつい 「目の前の事柄」 とは別の 『正解』 を求めて
いろいろと思いを巡らせる傾向があります。
人間の持つこうした「傾向」を踏まえて、宗教を考えてみようと思います。
・ 「キリスト教」 その3つの要素 私がカトリックに出会ったのは、敗戦後間もない 1946 年でした。 近くの知らないお宅で 『幻燈』 (今風にいえば、スライドショー?)でマンガが見られるという友人の話に誘われ、 そのお宅に行ったのでした。 集まってきたのは近所の顔見知りの友達ばかり。 イタリア人の神父が来ていましたが、『幻燈』 のマンガや、聖書の物語のナレーションは そのお宅のご主人(カトリック信者)が、面白おかしく聞かせてくれたのでした。 こういう出会いがきっかけで、私は教会に足を運ぶことになったのですが、そうした友人 の中で、カトリック信者になったのは二人ほどでした。 カトリックの勉強(?)をする中で、3つの要素ないし側面があることに気づきました。 第1は、いわゆる 「教義 : 信ずべきことがら」、第2は 「戒律 : 守るべきことがら」、 第3は、「秘跡 : 神の恵みをいただく方法」≒「宗教儀式ないし祈り」。 一般的に、キリスト教という言葉を聞いて、日本人がイメージするのは、「教会堂」とか そこで日曜日などに行われる「ミサ」 (プロテスタント教会であれば、日曜礼拝)、そして 「聖書」や「讃美歌」といった事柄ではないでしょうか? いわゆるキリスト教国では、こどもの頃から、そういう形で教会・キリスト教に馴染んで いくわけですから、それ自体は不自然なことではありませんが ・・・ つまり、先ほどの3つの側面のうち、おおむね第3の「宗教儀式ないし祈り」という部分、 日曜日を中心にイメージされる 『教会での礼拝ないし儀式』 です。 実際、「日曜日に、一度、教会に行ってみたいのだが・・・」 という知人が稀にいます。 私は、あまり積極的に勧めることはしません。 宗教的儀式は、馴染みのない方には 意味の分かりにくいもので、多くの場合、「なんのこっちゃ・・・」 という結果に終わって しまうことが懸念されるからです。 ミサ中の立ったり座ったりの所作、聖体拝領の際の信者と未信者の対応の違いなど、 初めての参加者には当惑の連続 ・・・ という印象が強いことと思います。 加えて、一般的にカトリックの神父の(ミサ中の)説教はそれほど感銘を受けるほどの ものではなく、実にありきたりの内容でがっかりするケースが多いのです。 (^_^); いっそ、説教の上手な神父の話を、ネットなりで配信した方がよほどマシでしょう。 こういう私の見解に同意なさらない信者さんも多いと思います。 しかし、私の信仰的 感覚・感性からいえば、キリスト教との出会いを、儀式(カトリックでは 「典礼」 と呼んで います)から始めるのはどうかな? という思いがしてならないのです。 この第3の側面は、すでにキリスト教に入信したクリスチャンの、日常的な信仰生活の パターンとして(例えていえば、メトロノームのような)意味を持つもの ・・・ というのが、 私の理解です。 例外的に、病気などで非常にこころを痛めていらっしゃる場合などでは、キリスト者が その方に寄り添い、ただひたすらに祈る(それも単純な祈り、例えば Ave Maria ・・・ など) という方法が好ましいケースのあることは、私も経験的によく知っているところです。 これは、心と体を慰め・癒す「祈り」のスタイルとして、とても意味深いものです。  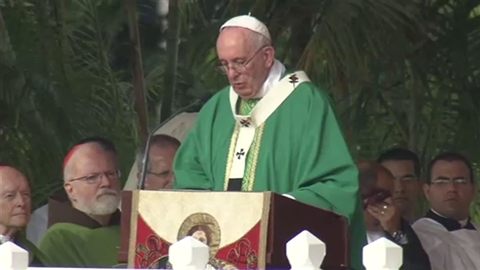 ・ 窮屈な戒律尊重主義 キリスト教に親しむ中で、一番当惑したのは、第2の側面 : すなわち毎日の生活の中 での禁忌事項があまりにも多く、しかも厳しいことでした。 まず 「十戒」 と呼ばれるもの。 キリスト教の神のみを礼拝し、異教の神仏の礼拝を 禁じるのは当然として、「父母を敬え」 「姦淫するな」 「盗むな」 「偽証するな」 といった 道徳的なテーマが事細かに規定されており、若い人々にとってはとりわけ「性」に関する 禁忌事項が厳しい ・・・ というのが、とても強く印象づけられたのでした。 ヘルマン・ヘッセの小説 「車輪の下」 では、そういうキリスト教社会の重荷に苦しむ 若い主人公が描かれており、私も大いに共鳴を覚えたものです。 それにも増して厳しく ・ 事細かなのは、「教会の6つの掟」というものです。 日曜日にはミサに参加しろ、遅刻は「奉献」という部分より前なら「小罪」だが、 それ以降なら「大罪」・・・ すなわち地獄行き! 「告解」(懺悔)が必要。 年に一度は「告解」「聖体拝領」をすべし。 定められた日には「大斎」(断食)、金曜日には「小斎」(鳥獣の肉食を禁じる)を守れ。 小斎に関しては、食した鳥獣肉の量が 60g 未満なら「小罪」、60g 以上なら「大罪」という 説明までありました。 また「クジラ」は鳥獣か? 魚か? という議論が真面目になされて いたのでした。 キリスト教に関心を示した人々に、いきなり、キリスト教のこういう側面を説明する というのも、これまた全く的外れなことでしかないのです。 以上のようなことから、初めてキリスト教に関心を持った方には、信仰の第2・第3の 側面ではなく、第1の側面、すなわちキリスト教の教義(信仰告白の内容)を説明して いくことが適当だと考えます。  カトリックでは、以前は 「公教要理」 というコンパクトな 「入門書」 があり、私もそれで キリスト教を学んだのですが、1960年代の 「第2バチカン公会議」 以降は、そういう ツールが尊重されなくなり、現時点、多くの神父は 「聖書勉強会」 的なもので、それを 補っていることが多いようです。 私の印象としては、聖書をいきなり読み始めるのは、多くの日本人にとっては、かなり 「違和感」があると思います。 聖書独特の言い回し、福音書相互間での記述の食い違いなど、当惑の素材がいっぱい! あるいはパウロ書簡での「現代的感覚からはあまりにもかけ離れ過ぎた記述」(例えば、 I テモテ 2章 11節以下など)によって、聖書への違和感を増幅させることが心配される からです。 先週の 「2枚の硬貨で 150円」 の問題を思い出してください。 あそこには、2枚の硬貨の写真が提示されていました。 これが実に「曲者」でした。 このような問題設定において、こういう写真がいきなり 提示されていると、人々は、この写真とは異なる「組み合わせ」が、正解なのだ ・・・ と (勝手に)思い込んでしまうものです。 この問題提示部分には、こういうトリックが組み込まれていることを、すぐに見抜く 人は、少ないだろうと思います。 写真の提示で、読む人をまんまと別のイメージの 世界に誘い込んでいる点が、この出題者のすごい「悪知恵?」 or 「悪戯心」です。 次に、『その内 一方が 50円玉でないとすると 』 という ≪言い方≫ で、人々を妙に 混乱に誘導しています。 もし、この表現が 『その内 一方が 50円玉だとすると 』 となっていれば、これは誰の 目にも迷いなく正解を認識させることでしょう。 つまり、物は言いよう であり、視覚はしばしば騙される という重大な事実が、 あの出題には組み込まれていたということです。 キリスト教との出会いをどう「演出」するか ・・・ というテーマにおいても、上手な方法と、 下手な方法とがあるということ。 先週紹介したあの事例から、私はそれを強く認識させられたのでした。 |

| 今週の | 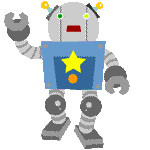 | リメンバー | 私は参加しなかったのですが、9月に熊本で 同窓会がありました。 1951年に同期入社した 仲間たちの 《最後の》 同窓会でした。 その記念冊子を頂戴して当時を思い出しました。 全員が中学卒業で採用され、今年傘寿を迎えた 面々です。 総員 180名、 当日の参加者は 35名。 109名が名簿登録されており、物故者は 55名、 連絡のとれない方が 16名となっています。 1/3 程の方が亡くなっており、健康上の理由で 参加を見送った方も多かったことから、80歳と いう年齢の平均像が伺えます。 親許を離れ、全員が木造の寄宿舎住まい。 空腹を抱えて『トン・ツー』の訓練に明け暮れた 少年・少女が、こうして傘寿を迎えたのですから、 有難いことではあります。 当時の研修所の土地も売却され、スーパー・ マーケットの建設が進行中の由。 老兵は消えいくのみ ・・・ という感じです。 |
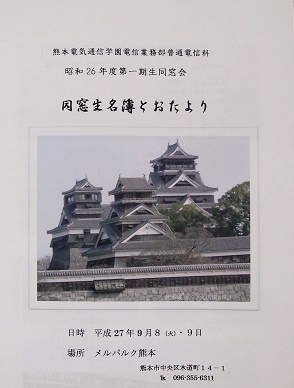
|