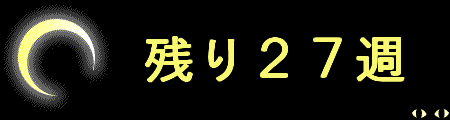☆ 2月第2週 ☆ 2015/02/05 ~ 02/11
映画 『マエストロ』 を観て思ったこと
原作がコミックで、西田敏行が型破りな指揮者を演じるという触れ込みのこの映画。
クラシック音楽がテーマで堅苦しい ・・・ とは決して思わないでください。 ハチャメチャな部分と
ラストの意外性とで大いに楽しめる「娯楽作品」なんです。
●役者さんが頑張ってます! コンサート・マスター役の松坂桃李は、撮影の1年前からヴァイオリンの手ほどきを受けたそう ですが、それだけの準備を積み重ねたことが納得できる「本気度」がいたるところに垣間見えます。 もちろんプロの音楽家も競演していて、実は、私の知人のご子息(ヴァイオリニスト)が出演して おられたのには、本当にびっくり!! 第2ヴァイオリンのトップ奏者をやってた 朝来桂一 さん です。 ちなみに、映画の中のオーケストラは、最近の楽器配置ではなく、かなり古いスタイルです。 映画では、第1ヴァイオリンを左に、第2ヴァイオリンを右に配置しています。 現代のオーケストラでは、左から、第1ヴァイオリン・第2ヴァイオリン・チェロ・ビオラという 配置が多いようです。 このほか、曲によっても配置の違うケースがいろいろ見られます。 ●楽譜はそのままでは面白くない! 映画の中で、指揮者がしきりに使うのは、ただ楽譜通りに弾いてもダメだというセリフ。 「相手を殺すような・・・」とか、ヴァイオリンの弓の「3本の糸で音を出せ」といった 非常に過激な言葉の数々。 音大の授業ならともかく、プロのオーケストラ奏者を相手にこういう 練習風景があるのかどうかには疑問を覚えますが、要は、楽譜どおりに弾いているのではダメ! という強いメッセージは十分に伝わってきます。 演奏という作業では、楽譜から何を読み取るか?というのは、大きな課題ですね。 演奏者が、楽譜から読み取るものは、一人ひとりの演奏者で違いますし、時代によっても読み取り 方の違いがあるようです。 オーケストラでは、それを指揮者がリードしていく訳で、同じ曲を同じ 楽団が演奏しても、印象の違うものに仕上がるところが、演奏会通いの醍醐味のひとつなのです。 歌の練習を通じて、私も実感していることですが、単に楽譜通りに正確に歌うというだけでは、 その曲の味わいが伝わらないのです。 もちろん基本的な発声法とかは大事なことですが、 それプラス演奏者の感性なり人生観なりが滲み出るようにするのが、やはり目標ですね。 ●みんな違って、みんないい! 同じ楽譜を見ていても、演奏者によってその解釈や表現方法が違ってくるのは当然のこと。 このことが分かれば、ある本に書いてあることについても、読者一人ひとりごとに、受け取り方には 違いが出るであろうことも、素直に納得することができます。 宗教における「聖典・経典」に関しても、同様に、解釈の違い(多様性)が発生してもそれは当然な ことの筈です。 それが「当然」とされないところに、宗教の分野でのややこしさがあるようなのです。 例えば、キリスト教の場合、「新約聖書」の読み方を巡って、いろいろな解釈の違いが、教会(教派) ごとに存在します。 一例として、『イエスの母:マリア』を巡って、カトリック教会とプロテスタントの 教会とでは大きく喰い違っています。 ここでは細かくは触れませんが、その辺りをご存知ない方が 映画やドラマを演出すると、プロテスタントの教会や学校等にマリアの絵や像が置かれていると いった珍現象が起こります。 西方教会と東方教会の違いなどは、さらに日本人には馴染みのない ところでしょう。 (一例として、「十字(架の印)の切り方」)   イスラム教でも、スンニ派・シーア派という違いがあるようですが、私はよくは知りません。 いろいろな問題を巡って、数多くのグループごとの違い(特徴)は避けられないことなのですね。 そういう違いは「認められない・自分だけが正しい」という頑なさは、それなりの根拠があるもの かもしれませんが、それを押し通すことで何が起こるかと言えば、もう紛争と流血と狂気の数々で しかありません。 『みんな違って、みんないい』という言葉、個人的には好きではないのですが、相手との折り合いを 優先させて、とりあえずの「正面衝突」にブレーキをかける ・・・ という対処法は、やはり尊重すべき 考え方だというしかないと思います。 日本的な「なぁ、なぁ主義」という意味よりは、当座の衝突・激突をまずは抑え、何が本質的に問題 なのかを話し合う・吟味し合う状況を互いに作り出すための方便としてであっても、こういうスタンス をとりあえず受け入れる寛容さが何よりも大切なのです。 原理主義だけでは問題解消はできない ことに気づくことから、先ずは踏み出したいものだと、つくづく思い知ったこの頃です。 |

外国で観たオペラ ② : プッチーニ 「トゥーランドット」
このオペラ、日本で知られるようになったのは、アリア【誰も寝てはならぬ】が、アイススケート競技の
曲として取り上げられたのがきっかけでした。 全曲を聴いた・観たという人は少ないのでは?
二度目の海外旅行は、1990年春、銀婚記念で西ヨーロッパに行ったもの。 団体ツアーですが、参加者は 音楽好きの4組の夫婦という小人数で、ツアー・コンダクターも音大卒のベテランの方でとても快適でした。 当初は、ミラノ・スカラ座で「トスカ」を観るというのがうたい文句でしたが、いろいろ事情があってチケットが 入手できず、参加者が激減、結局4組のみの参加になったという いわくつき の旅でした。  スカラ座前の広場 スカラ座前の広場ベネチアでもその時期には、オペラ上演がなく、オペラ鑑賞はドイツまで持ち越しです。 ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場は、サン・フランシスコのオペラハウス以上に、着飾った人々が多く、 これが本場欧州のオペラハウスの雰囲気なのかと、圧倒されました。 ただ、隣席のご婦人の香水の強烈さには、文字通り辟易! このオペラ、中国の物語だけに、こてこての中国趣味の舞台装置になりがちですが、この公演は抽象的な 雰囲気の舞台づくりで、僅かに、ピン・ポン・パンの3人の衣装だけが中国風なデザインでした。 個人的には、こういうステージでこの曲を聴けたのはラッキーでした。 (音楽に集中できたので)
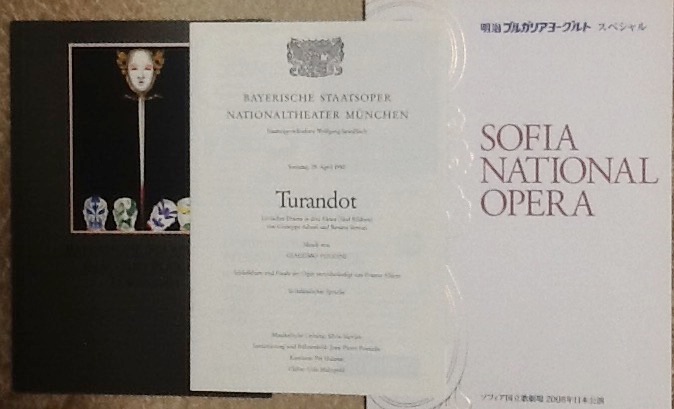 |
| 《 レクィエム 》 | ボランティア仲間の U さんのお通夜にお参りして来ました。 同年輩のメンバーが亡くなるのには、とりわけ心が痛みます。 山旅とカメラが好きだった方で、記念に一枚の山の写真を頂いてきました。 テニスやバドミントンも楽しんでいた U さんの方が、虚弱な私よりも早く 逝かれたことに、世の無常を覚えるのでした。 合掌。 |