

| 1.<イエス・キリスト>は 名前ではない  |
イエス・キリストという言葉を聞いて、姓はキリスト・名はイエスと思っている人がいるかもしれませんが、 そうではないのです。 これは<イエス = キリスト すなわち救い主>という「信仰宣言」なのです。 イエスという人物が、2000年ほど前に、現在のイスラエルに生きていたことは、まず間違いない事実だったといえますが、 それがどのような人物であったかはよく分かっていません。 こう書くとクリスチャンたちから非難されると思いますが、私たちが教会(キリスト教)を通じて知ることができるのは 救い主<イエス・キリスト>についての事柄であり、決して歴史上の人物であるイエス様についてではありません。 つまりイエスという人物についての事実をどれだけ知っているかといえば、相当に疑問があると思います。 ここではそういう視点から、イエスという人物の本当の姿を探る努力をしてみたいと思います。 | |||||||
| 2.「史的イエス探究」 という立場  |
イエス・キリストという表現が、イエスを救い主として受け入れるという信仰宣言であることは先ほど書いたとおりです。 私たちがキリスト教という宗教を通じて知るイエスというお方は、あくまでも信仰の対象としてのイエス様です。 もちろんイエスを神の子として崇め、自分の救い主として信仰することはキリスト教の立場からは当然です。 私自身、60年ほどのカトリック信者としての日々を通じて、他のクリスチャンと同様に<イエス=キリスト>という 信仰宣言を表明し続けています。 しかし一方では、そういう信仰上のイエス、すなわちキリストとしてのイエスではなく、歴史上の人物としてのイエスを 明らかにしたいと考えた人々もいます。 これが「史的イエス探究(研究)」という考えです。 イエスを信仰の立場からではなく、歴史的な「存在」・「人物」として明らかにしてみようという熱意は、私にも理解できます。 クリスチャンの中にも、そういう立場を支持する人がある一方、あくまでもそういう「探究」は信仰の補助的な手段ではあっても、 それがそのまま信仰につながるとは言い難いという立場の人々もたくさんいます。 昨年の秋、上智大学のキリスト教文化研究所が主催した「聖書講座」のテーマは「史的イエス研究の射程と限界」というものでした。 テーマからは、「探究(研究)」の意味を認めつつも、信仰の立場からは限界があるという主張が読み取れるように思います。 | |||||||
| 3.「まことの人」である イエスを考える  |
史的イエス探究が、必ずしも<信仰への道のり>を前提にしているとは言えないとしても、それがまったくの的外れなものとは 私には思えません。 というのは、「正統派キリスト教」の教義には「イエスは<まことの神>であり、<まことの人>である」というキリスト両性論と いう主張があるからです。 これは、初期のキリスト教の中に、「イエスは神であり、人としての姿をとったのはあくまでも仮の姿でしかなかった」と主張する人や、 逆に「イエスは人間でしかなかったが、その立派な生き方によって、神がご自分の子として認めるにいたった」と考える人もいたようです。 そういういろいろな意見を整理するために、何度か大規模な教会会議(公会議)が開かれています。
*参考書籍 ジェラール・ベシエール「イエスの生涯」(創元社) このように、正統派キリスト教では 「イエスは真の神=神の子」であるとともに「イエスは真の人=仮の姿ではなく、正真正銘の人間」 と教えており、「イエスというペルソナ(人格という表現は不正確です、カトリックでは位格とよんでいる)の内に、神性と人性とを 兼ね備えている」という立場です。 私は、この「まことの人」という部分に注目したいと思っています。 私にとってイエスは「神であり、同時に人である」ことから、両方の面からイエスというお方の姿を見据えたいと思うのです。 「まことの神」としてのイエスの姿は、教会が一生懸命教えてくれました。しかし「まことの人」としてのイエスの姿を、 教会は必ずしも十分には見せてくれていません。 ということで、以下の私のささやかな考察は、いわゆる「史的イエス探究」とは一線を画すものです。 あくまでも「神の子イエス」が地上で見せた姿=「まことの人」としての姿を、自分なりに確かめてみたいという熱望です。 それは信仰の面からも大事なことだと確信します。 こういう立場をご理解いただければ幸いです。 | |||||||
4.イエスの誕生について |
「まことの人であるイエス」を、その誕生の時点で見るとき、少なくとも聖書(厳密には福音書)は、何も述べていないに 等しいと思われます。 イエス誕生の時期は、決して西暦1年ではありません。 そのあたりのことを、中丸明「絵画で読む聖書」(新潮社) は、次のように記しています。 西暦ADを考え出したのは、数学と天文学に通じていたローマの修道院長、ディオニュシウス・エクシグウス (500年頃〜560年)である。 西暦525年に彼は、日付をきめる基準としてAD、すなわち Anno Domini (「われらが主の年」の意味) を考案した。 のちにローマ教皇グレゴリウスがこれを採用したのだが、エクシグウスにはちょっとした計算ミスがあった。 彼は、イエスが誕生した年をローマ建国の753年後としたのだが、「福音書」などの記述などから聖書学者たちが 検討したところ、イエスが生まれたのはヘロデ王が死ぬまえだったらしく、イエスはBC4年以前に生まれていたらしい。 ということになっている。 またマタイ福音書によるとイエス誕生の直後、ヘロデ王による<嬰児虐殺>があり、イエス一家はその難を避けてエジプトに逃避 したということになっています。 一家がイスラエルの地に戻ってくるのは、ヘロデ王が死んだ後ということです。 ところがルカ福音書によるとそういう事柄には一切触れず、エルサレムの神殿で律法に定められたもろもろの儀式(割礼など)を 無事に済ませて、両親ともども平穏に故郷ナザレに戻って行ったことになっています。 ということで、イエスの誕生に関しては聖書が<事実>を記述しているとは言い難いのです。 | |||||||
5.イエスの死について
|
では、イエスの死についてはどうでしょうか? 4つの福音書には、詳細部分は別にしてひとつだけ確実に共通する要素があります。 それはイエスが十字架刑によって死に至ったという点です。 パウロは十字架刑を 「キリストはわたしたちのためにのろわれた者となって、律法ののろいからわたしたちをあがない出してください ました。−−「木にかけられた者はすべてのろわれた者」と書き記されているからです。−−」(ガラテア3章13節) と説明しています。 これは「まことの神」であるイエスに関する記述ではあっても、「まことの人」としてのイエスに関するものとはいえません。 「まことの人」イエスの十字架刑の意味は、別の視点から探究されるべきでしょう。 | |||||||
| 6.十字架刑の意味を、 「まことの人」の視点 から考える 
|
当時のユダヤは、ローマ帝国の支配下にありました。 紀元前4年ヘロデ王が死んだ後、国内のあちこちでユダヤ人による反ローマの反乱がおこり、最終的に帝国はそれらを平定し、 ヘロデの王国を三分割して傀儡政権を置くとともに、ローマ総督の監視のもとに置いています。 ローマによるユダヤ支配という<歴史的事実>を踏まえて、イエスの時代・イエスの死<十字架刑>を考えることは決して 無意味ではないのです。 十字架刑が、実はローマの処刑方法であり、決してユダヤの律法による処刑方法ではなかったという<事実>を知ったとき、 私は「まことの人」であるイエスの生き方・生き様に目覚めた気がしました。 参考書籍:半田元夫「イエスの死」(潮新書) ローマ帝国はこの処刑方法を、重大な犯罪者、逃亡奴隷や叛徒などに用いたということです。 福音書は、イエスと一緒に十字架にかけられたふたりを「盗賊」などと記していますが、歴史の現実を顧みるなら、 そのような理由での十字架刑など考えられないというのが真相のようです。 つまり福音書は、意識的に「ローマへの反逆者としての処刑」という事実に目をつぶってイエス伝を記述しているということになります。 ここからは「まことの人」イエスの姿は見えてきません。 | |||||||
| 7.イエスはローマへの 反逆者か?  |
「では、イエスは反ローマ運動の革命家であったのか?」と問われれば、私はそうは考えていません。 というのもイエスの行動のすべて(あるいは主たる狙い)が、反ローマ帝国という政治的な意図のもとに展開されていたとすれば、 その進め方はあまりにも荒唐無稽であり、計画性のない夢物語でしかないと思えるからです。 帝国からのユダヤ民族の解放を本気で考える「革命家イエス」であれば、福音書から垣間見えるような<ユダヤの伝統・律法主義 批判>をあれほど熱心にとりあげることはなかったでしょう。 「革命家イエス」の真の敵は、ユダヤの支配者ではなく、ローマ帝国だったはずです。 ところが、福音書の記述にはそういう傾向は皆無です。 前述の半田氏の最後の文章に次のようにあります。 しかし、イエスが政治犯としてピラトゥスによって十字架刑に処せられたことは、動かしがたい事実として残る。 イエス自身革命的意図をもっていたかどうかは別問題として。 私は、イエスが反ローマの叛徒だとは考えませんが、イエスの「律法主義批判・ユダヤの伝統批判」が、ユダヤ社会上層部の 反感を買い、彼らの策謀のもとでローマ兵による逮捕・処刑につながっていったと理解するようになりました。 | |||||||
| 8.イエスはユダヤの 伝統・律法を どのように批判 したか?  |
これは福音書から拾い出しても枚挙のない多さでしょう。 いわく、
当時のユダヤ社会が、ユダヤ教と言う宗教的権威にがんじがらめであったことは明らかです。 イエスはそういう「宗教的権威・宗教的呪縛」を徹底的に批判しています。 それは「ユダヤ教のこういう部分を刷新したい」とか「あたらしい宗教を始めよう」という類のものではなく、 むしろ反ユダヤ教といってもいいような過激なものだったと思われます。だからこそ上記(マルコ3章)のような イエス殺害の協議につながっていったのではないでしょうか? イエスは決して「キリスト教の創立者」ではありません。むしろ「脱宗教」の理念をもった改革者だった のではないでしょうか。 | |||||||
| 9.イエスを旧約の延長 線上で見ることを やめませんか? 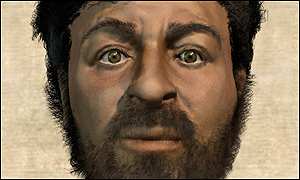 |
キリスト教は「ユダヤ教」という根っ子に接ぎ木して誕生した宗教だと考えることができます。 1) マタイ福音書で顕著な傾向ですが、イエスにかかわる話題を紹介したのちに、 「これは旧約の預言が実現するためであった」という文言がしばしば使われています。
2) パウロ書簡でもイエス様を旧約時代のユダヤ教の伝統を刷新し完成させるお方だという意味の記述が見られます。
3) 教皇ヨハネ・パウロ2世は、次のように発言なさっています。
以上のようなことから分かることは、ユダヤ教とキリスト教とは連続性を有しているという認識です。 ユダヤ教の伝統(旧約聖書の世界)は尊いものだが不完全なもの、イエスの登場によってそれは刷新(完成)され・新しい 展開をしたのがキリスト教であるという主張でしょう。 はたしてそうなのでしょうか? 私にはそうとは思えないのです。 イエス様が、ユダヤ教の伝統(旧約)の完成者であるなどというのは妄想であり、そういう思い込みから抜け出ることが イエス様の真意をただしく受け止めることだと私は思うようになりました。 イエス様の言いたかったことは、ユダヤ教をはじめとする諸宗教が神を誤解しているという点を明らかにすること だったと思います。 宗教は、神と人間の関係を「裁く神:審判者、罰を下す権力者」と理解するところから出発していますが、イエス様は それを否定なさっていると理解します。 神は人をその行いの善悪で差別することなど絶対になさらない。 それは「ぶどう園の労働者のたとえ」や「放蕩息子のたとえ」で明らかだと私はすでに指摘 しました。 私たちは、神を「審判者:罰を下す権力者」として仰ぎ見るのではなく、ご自分が創造なさったすべての存在(私たちと 全宇宙)を完璧に包み込んでいらっしゃる方だと信じなさい ・・・ イエス様はそう教えて下さっているというのが 私の イエス信仰 の原点であり、核心なのです。 |