大部分の人は「オス(メス)」として生まれ、「男(女)の子」として育て
られています。
2つの区分・区別は無理なく重なっていると自己認識する人々が多いのです。
しかし、自分がそういう認識を持っているから、100%の人がそうなのだと決
めつけることは正当ではありません。
現実に、自分が「オス」か「メス」かを自覚できずに苦しんでいる人々すら
いるのです。
吉永みち子著「性同一性障害」には、次のような記述があります。
森田氏の戸籍上の性別は男である。背広とネクタイといった男性性を
表す服装は嫌いだと言うが、TシャツにGパン。髪も短い。がっしり
として体型からも声からも、誰もが疑いなく男性だと思うだろう。外
から見たら当然のように男でも、森田氏本人は、どうしても自分が男
とは思えない気持ちを内に秘めて生きてきた。ちょっとした懸賞の応
募葉書にも、アンケート用紙にも、必ずといっていいほど性別を書き
込む欄がある。外国に行くにも、履歴書を書くにも、男か女どっちか
に○をつけなければならない。
ほとんどの人は、機械的に男や女に○をつける。改めて考えたり、そ
の度に迷ったりする必要のない事柄が、森田氏にはペンを持つ手が思
わず止まるほどの何かをつきつける。
「男に○をつけます。戸籍が男と記載されているから。でも、その度
に激しい葛藤が心の中に生まれるんです。男に○をつけたくない。で
も、それだからといって、女に○をつけたいのかといわれれば、そう
いうわけではないんです。若い頃は、男性用のトイレを使うのは苦痛
でした。誰もいなければいいんですが、誰かいたりすると入れない。
男女併用のトイレひとつしかない喫茶店なんか行くと、うれしかった
です。」
その感じは保育園の頃からだという。
トイレの前まで行っても、他の男の子が入っていると、便器は複数あ
ってもトイレの中に入ることができない。次々と男の子がやってくる
と、トイレの前まで行っていながらお漏らしをしてしまう。
この森田さんの場合、「男性的な特徴が現われてくるのは、イヤだったが、
かといって女性的になりたいとも思わない。女性の服装をしたいという気も
ない」ということです。
自分の性をはっきりと認識できない、こういう人々が確かに存在するのです。
「どちらの性か自分の中で決められないのなら、このままで生きていこう。
それを認める社会であってほしい。」これが森田さんの願いだそうです。
次に、自分の体に見る「オス、メス」の区分をはっきり認識できてはいるが、
その区分を自分の気持ちや生活の中で受け入れること(性の自認)に違和感
を抱いている人々がいます。
性同一性障害と呼ばれるこの人々は「性転換手術」を望むほど、自分の体が
もつ「オス(メス)」に対して深刻な違和感を味わい、悩んでいます。
つまり、体の性とこころの性とが一致しないという苦しみです。(トランス
セクシュアル)
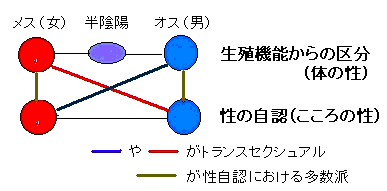 さらには、「男らしさ」とか「女らしさ」というジェンダーの区別について
行けない人々も大勢います。トランスジェンダーと呼ばれるこういう人々に
対して侮蔑的な「オカマ」や「オナベ」という呼称が使われています。
また、ジェンダーフリーとして、既存の「男らしさ、女らしさ」の観念を離
れて生きようとする人々も、社会の冷たい視線や差別に耐えなくてはならな
い状態にあります。
さらには、「男らしさ」とか「女らしさ」というジェンダーの区別について
行けない人々も大勢います。トランスジェンダーと呼ばれるこういう人々に
対して侮蔑的な「オカマ」や「オナベ」という呼称が使われています。
また、ジェンダーフリーとして、既存の「男らしさ、女らしさ」の観念を離
れて生きようとする人々も、社会の冷たい視線や差別に耐えなくてはならな
い状態にあります。
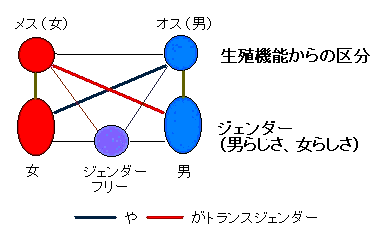 あるいは、普段は「男、女」の区別に従って生きていても、それに 100% の
納得がいかず、息抜きの時間を異性装で過ごす人もいます。(トランスヴェ
スタイト)
こうして見ると人の性は生物学的な「オス、メス」の区別と、社会的な役割
としての「男らしさ、女らしさなどの性差」(ジェンダー)という多層性を
有しており、その重なり方の食い違いが『性の多様性』という事象を生み出
していることに気づきます。
ジェンダーすなわち社会的な「男(らしさ)、女(らしさ)などの性差」は
ライフスタイルに関する問題です。そして、それは性的指向での「同性愛」
につながる要素を持っています。
これまで同性愛(ゲイ、レズビアン)はもっぱら性行動として語られてきま
した。ホモセクシュアルという言葉は、それを指していると思われます。
しかし、子供の遊びの段階から体験し始めているこの問題は、もっと幅広い
観点から、人の生き方・ライフスタイルに深く関連したものとして捉えてい
くことが必要なようです。
人が社会の中でどのように生きていくかは、決して「男女の二者択一」だけ
の単純な選択肢だとは言い切れないのです。
また「男」としての生きかたや「女」としての生きかたを、固定的に考える
ことも現実に合わないことを知るべきです。
ライフスタイルとしてのジェンダーに連なるゲイやレズビアンは、人の生き
方のひとつのあり様として、素直に受容して当然なことなのです。
道徳や宗教が口を出す領域では、決してありません。
あるいは、普段は「男、女」の区別に従って生きていても、それに 100% の
納得がいかず、息抜きの時間を異性装で過ごす人もいます。(トランスヴェ
スタイト)
こうして見ると人の性は生物学的な「オス、メス」の区別と、社会的な役割
としての「男らしさ、女らしさなどの性差」(ジェンダー)という多層性を
有しており、その重なり方の食い違いが『性の多様性』という事象を生み出
していることに気づきます。
ジェンダーすなわち社会的な「男(らしさ)、女(らしさ)などの性差」は
ライフスタイルに関する問題です。そして、それは性的指向での「同性愛」
につながる要素を持っています。
これまで同性愛(ゲイ、レズビアン)はもっぱら性行動として語られてきま
した。ホモセクシュアルという言葉は、それを指していると思われます。
しかし、子供の遊びの段階から体験し始めているこの問題は、もっと幅広い
観点から、人の生き方・ライフスタイルに深く関連したものとして捉えてい
くことが必要なようです。
人が社会の中でどのように生きていくかは、決して「男女の二者択一」だけ
の単純な選択肢だとは言い切れないのです。
また「男」としての生きかたや「女」としての生きかたを、固定的に考える
ことも現実に合わないことを知るべきです。
ライフスタイルとしてのジェンダーに連なるゲイやレズビアンは、人の生き
方のひとつのあり様として、素直に受容して当然なことなのです。
道徳や宗教が口を出す領域では、決してありません。
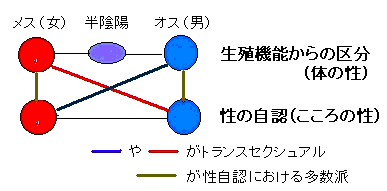 さらには、「男らしさ」とか「女らしさ」というジェンダーの区別について
行けない人々も大勢います。トランスジェンダーと呼ばれるこういう人々に
対して侮蔑的な「オカマ」や「オナベ」という呼称が使われています。
また、ジェンダーフリーとして、既存の「男らしさ、女らしさ」の観念を離
れて生きようとする人々も、社会の冷たい視線や差別に耐えなくてはならな
い状態にあります。
さらには、「男らしさ」とか「女らしさ」というジェンダーの区別について
行けない人々も大勢います。トランスジェンダーと呼ばれるこういう人々に
対して侮蔑的な「オカマ」や「オナベ」という呼称が使われています。
また、ジェンダーフリーとして、既存の「男らしさ、女らしさ」の観念を離
れて生きようとする人々も、社会の冷たい視線や差別に耐えなくてはならな
い状態にあります。
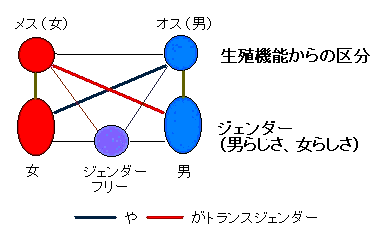 あるいは、普段は「男、女」の区別に従って生きていても、それに 100% の
納得がいかず、息抜きの時間を異性装で過ごす人もいます。(トランスヴェ
スタイト)
こうして見ると人の性は生物学的な「オス、メス」の区別と、社会的な役割
としての「男らしさ、女らしさなどの性差」(ジェンダー)という多層性を
有しており、その重なり方の食い違いが『性の多様性』という事象を生み出
していることに気づきます。
ジェンダーすなわち社会的な「男(らしさ)、女(らしさ)などの性差」は
ライフスタイルに関する問題です。そして、それは性的指向での「同性愛」
につながる要素を持っています。
これまで同性愛(ゲイ、レズビアン)はもっぱら性行動として語られてきま
した。ホモセクシュアルという言葉は、それを指していると思われます。
しかし、子供の遊びの段階から体験し始めているこの問題は、もっと幅広い
観点から、人の生き方・ライフスタイルに深く関連したものとして捉えてい
くことが必要なようです。
人が社会の中でどのように生きていくかは、決して「男女の二者択一」だけ
の単純な選択肢だとは言い切れないのです。
また「男」としての生きかたや「女」としての生きかたを、固定的に考える
ことも現実に合わないことを知るべきです。
ライフスタイルとしてのジェンダーに連なるゲイやレズビアンは、人の生き
方のひとつのあり様として、素直に受容して当然なことなのです。
道徳や宗教が口を出す領域では、決してありません。
あるいは、普段は「男、女」の区別に従って生きていても、それに 100% の
納得がいかず、息抜きの時間を異性装で過ごす人もいます。(トランスヴェ
スタイト)
こうして見ると人の性は生物学的な「オス、メス」の区別と、社会的な役割
としての「男らしさ、女らしさなどの性差」(ジェンダー)という多層性を
有しており、その重なり方の食い違いが『性の多様性』という事象を生み出
していることに気づきます。
ジェンダーすなわち社会的な「男(らしさ)、女(らしさ)などの性差」は
ライフスタイルに関する問題です。そして、それは性的指向での「同性愛」
につながる要素を持っています。
これまで同性愛(ゲイ、レズビアン)はもっぱら性行動として語られてきま
した。ホモセクシュアルという言葉は、それを指していると思われます。
しかし、子供の遊びの段階から体験し始めているこの問題は、もっと幅広い
観点から、人の生き方・ライフスタイルに深く関連したものとして捉えてい
くことが必要なようです。
人が社会の中でどのように生きていくかは、決して「男女の二者択一」だけ
の単純な選択肢だとは言い切れないのです。
また「男」としての生きかたや「女」としての生きかたを、固定的に考える
ことも現実に合わないことを知るべきです。
ライフスタイルとしてのジェンダーに連なるゲイやレズビアンは、人の生き
方のひとつのあり様として、素直に受容して当然なことなのです。
道徳や宗教が口を出す領域では、決してありません。