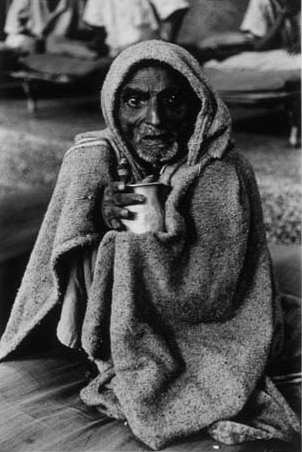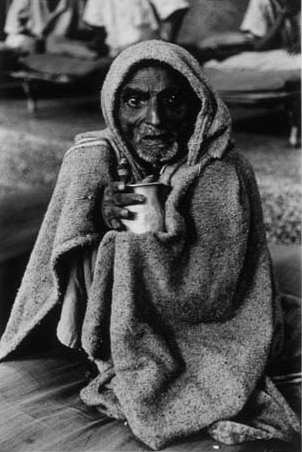私はこのテキストを、今年の待降節の黙想のテーマとして、幼いイエス様に捧げます。
そして、阪神大震災の際に作詞・作曲した自作の歌を、もう一度、こころに刻みたいと思います。
1. がれきの山に 草花を手向け
泣き崩れてる あの人の
肩を抱いて 涙流したあなた
そんなあなたの優しさを 今日も待っている人がいます
あなたの町に あなたの傍に
2. 粉雪舞う夜 避難所の床に
蹲ってる あの人に
笑顔見せて 話しかけたあなた
そんなあなたの・・・・・・
3. 水もガスもない 仄暗い部屋で
ひとり耐えてる あの人に
夕餉届け 灯り点けたあなた
そんなあなたの・・・・・・
呼んでいる声、それはキリストの声。
|
|